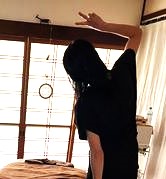コンポストや生ごみ堆肥が気になっている方、必見。
実際やってみて、なるべく簡単かつ継続できると感じたやり方をご紹介します。
生ごみ堆肥とは?
生ごみ堆肥とは、家庭で出た生ごみや野菜くず、落ち葉などの有機物を、微生物(菌ちゃん)の力で発酵・分解させた堆肥のことです。
ちなみに生ごみ堆肥の作り方は、嫌気性と好気性があります。発酵する時に空気に触れるか触れないかの違いです。
| 発酵の種類 | 作り方 | 特徴 |
| 好気性発酵 | コンポスト容器内で 生ごみを堆肥化 | 生ごみ堆肥づくりの基本。 酸素を必要とする好気性菌による生ごみの発酵。自然界の微生物の発酵はこの形がほとんど。場所を必要としないのでベランダでも可能。 |
| 好気性 発酵 | 畑に直接 生ごみを埋めて堆肥化 | 生ごみを直接土の中へ埋める一番簡単な方法。場所があればいいかも。状況により分解速度が変わる。 |
| 嫌気性発酵 | 密閉容器で発酵させてから、畑に埋める。 EMぼかしが代表的。 | 生ごみを嫌気性菌により、漬物状態にする方法。 |
私のおすすめは、コンポスト容器での生ごみ堆肥(好気性発酵)です。
以前、EMぼかしを用いた生ごみ堆肥を作っていましたが何度も失敗。失敗談はこちらから↓

生ごみ堆肥 メリット&デメリット
メリット
- 生ごみが減り、捨てる手間が省ける
- 生ごみを入れるゴミ袋の節約
- 自宅で栄養豊富な堆肥ができる
- 植物や野菜を育てた後の土の再生ができる
- 微生物の大切さがよくわかる
- 循環型くらしができる
デメリット
- 虫がわかないか不安(少し虫が湧くこともありました)
- 臭い(しっかり発酵していれば気になりません。むしろいい香りです。)
- 手間(面倒くさいと思ったことはありません。生ごみもコーヒーかすも堆肥になると考えただけで愛おしく感じ、豊かな暮らしができるような気さえします(^▽^))
おすすめ 生ごみ堆肥の作り方
用意するもの
コンポスト容器【通気性がある容器、チャック付きの不織布コンポストがおすすめ】

コンポスト基材【植物を育て終わった再生したい土 or 黒土・赤玉土・腐葉土を混ぜたもの】

有機物【生ごみ、枯れ葉、乾燥させた雑草】
微生物のエサ【米ぬか、余ったヨーグルトや納豆の容器に水入れたものなど】
軍手
スコップ
生ごみ堆肥の始め方
1.コンポスト容器の底面に土を入れる
植物を育て終わった再生したい土、もしくは黒土・赤玉土・腐葉土を混ぜたものを入れます。
底面に生ごみが付かないために入れます。
2.生ごみと土をよくかき混ぜて重ねる
生ごみと土の割合は1対1が基本ですが、だいたいで大丈夫です。米ぬかがあったら、一緒に入れます。
土が多ければ分解が早くなり、生ごみが多くなれば分解が遅くなります。
生ごみは小さく刻んだ方が分解が早く進みます。微生物のエサの米ぬかなどがあれば、分解が早まります。
気候要件では、気温が高い夏は分解が早く、気温が低い冬は分解がゆっくりになります。
状況に応じて、色々調節してみるといいですね。

3.表面に土をかぶせ、コンポスト容器の蓋もしっかり閉める
表面に生ごみが出ないように、土をしっかりかぶせます。生ごみが出ていると虫が湧く原因となります。
コンポスト容器の蓋の閉め忘れにも注意して、虫の発生を予防しましょう。
私は、写真のように不織布コンポストを二つ並べて、一つは生ごみコンポスト、もう一つにはかぶせる土を入れてあり、すぐに土が被せることができるようにしてあります。


4.時々かき混ぜて、乾燥していたら水分補給
毎回の生ごみ投入時にコンポスト内をよくかき混ぜます。
生ごみの分解に適した土は、土が湿っている状態が理想的。手でぎゅっと握ると形ができるけど、つつくとすぐ崩れてしまうくらいの固さが望ましいです。乾燥しすぎていると発酵しないので、気温が高い時期は水分を時々補給してあげます。この際、納豆の容器に水を入れてかけてもいいですよ。
5.コンポストいっぱいまで繰り返す
コンポストがいっぱいになったら、風通しの良い場所で生ごみが分解されるのを待ちます。
寒い時期はコンポスト容器をひなたにおいてコンポスト内の温度をあげたり、置く場所を変えてみるのもいいでしょう。
気温が高い時期は乾燥しやすいので時々水分量をチェックします。
時々コンポスト内をスコップでかき混ぜます。
6.コンポスト内の生ごみがなくなれば、完成
目安は夏場で1か月、冬場で3か月です。
コンポスト内をよくかき混ぜて、生ごみが消えていれば、完成です。
卵の殻は分解が遅く残ることが多いですが、そのまま培養土として使用できます。分解が遅いからと卵の殻を入れないのはカルシウムたっぷりですからもったいないです。
生ごみの分解途中では白カビが発生しますが、分解が進んでいる証拠ですので大丈夫です。香りもキノコのようないい匂いでします。